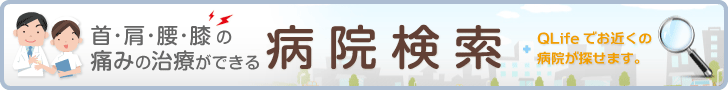インタビュー 遠藤 健司(えんどう・けんじ)先生
[インタビュー] 2014年7月01日 [火]

遠藤 健司 東京医科大学病院整形外科講師
1962年東京都生まれ。88年東京医科大学卒業。92年米国ロックフェラー大学に留学、神経生理学を専攻。95年東京医科大学霞ヶ浦病院整形外科医長、2004年東京医科大学整形外科医局長、07年から同講師。
大学病院は最新技術をダイレクトに患者さんに提供できる。休日のない忙しさでも、そこも医師としてのやりがいです。

「ネコのバランス感覚って、すごいですよね」と穏やかに遠藤先生が話しはじめます。
確かに、高い塀から飛び降りても見事に着地するネコの平衡感覚は誰もが認めるところです。その秘密は、脳から脊髄への神経伝達。それを分析・解明できたら、人間にも応用できるのではないか。どこの神経が損傷したらどんな障害が起こるのか、遠藤先生の留学時のテーマは「神経生理学」でした。留学先は、ノーベル賞受賞者を輩出している米国ロックフェラー大学。その昔、野口英世(のぐちのひでよ)も研究をしていたことで知られています。大学の図書館の前には彼の銅像が立っていました。
「当時、なかなか進まない研究に苦労しながら、銅像を眺めては、この地で彼もがんばったんだなと、しみじみ思ったものです」
神経の通り道である脊椎の病気は、医師からすると手術のやり直しのきかない難しさがありますが、「それだけに治ったときの喜びも大きい。そういう意味で魅力的な分野」と遠藤先生は語ります。
難しさを克服するために、いま遠藤先生が力を入れているのが、手術を安全に行うためのしくみの開発です。脊椎の手術で最も大きなリスクは、脊髄神経の損傷で麻痺(まひ)がおこること。腰部脊柱管狭窄症の手術ではほとんど心配はありませんが、首(頸椎)や背骨(胸椎)の手術などでは、慎重な対応が求められます。ところが、手術中は麻酔がかかっているので、麻痺がおこっているかどうかはわからないのです。
そこで開発されたのが「手術中に電気で神経を刺激して、手足にその情報が伝わっているかどうかを調べるしくみ」です。異常があるとモニターの波形が通常とは違った形になり、アラーム信号を発することで、麻痺を未然に防ぐような処置をすることができます。このしくみは数年前、健康保険が認められ、手術の現場で使われるようになってきました。今はこのしくみのさらなる改良に取り組んでいるところです。

整形外科は生活と密着した診療科とはよくいわれますが、最近は、手術法の進歩で、昔は質の高い生活をあきらめざるをえなかったような患者さんが、希望をもてるようになっています。「たとえば『腰曲がり』のおばあさんの手術」は背骨全体に及びました。その女性は骨粗しょう症のため、極端に腰が曲がってしまい、食事も立った姿勢でないと食べられず、歩くときも前を見ることができないほどでした。
「座って食べられない。首を立てて前を見て歩けない。そんな生活を想像してみてください」。かなりリスクは高かったのですが、本人のあまりのつらさと強い希望で、手術に踏み切ったといいます。「背骨を固定するネジなどの器具も進歩したので、可能になった手術です」
整形外科医には、大きく分けて「曲がったものを治すのが好きなタイプ」と、「神経や痛みに関心が高いタイプ」がいるそうです。「僕は後者で痛みの軽減を大切に考えるタイプ。患者さんの『痛みは我慢するもの』という思いを、まず取り払ってあげたい」という遠藤先生。最近では、アロマの香りによって、術後の患者さんの痛みを軽くできないかという研究が始まっています。看護師さんの提案による取り組みです。
「痛みを診ることは患者さんとのつながりをもつこと」に通じ、「根本は愛情」そして、医師としての原動力は「ピュアな気持ちに尽きます。たとえば、自分の肉親のつもりで、患者さんにとってのベストを一緒に考えていくということです」
入院患者さんがいるので、なかなか休日も取れず、自分の生活はいつも後回し。
「それでも、大学病院は最新の技術をダイレクトに患者さんに提供できるので、そこも医師としてのやりがいになっていますね」
(名医が語る最新・最良の治療 腰部脊柱管狭窄症・腰椎椎間板ヘルニア 平成25年2月26日初版発行)