会員限定この記事を読むと10pt 進呈!!
新規会員登録(無料) ログイン血中カリウム濃度の異常は致死的な症状を引き起こすことも
[ヘルスケアニュース] 2023/01/10[火]
腎機能が低下していると高カリウム血症になりやすい
カリウムは人体の細胞調節機能の維持に不可欠なミネラルで、不足しても多すぎても体に異常をきたします。特に注意したいのは、血液中のカリウム濃度が正常よりも高い値を示す高カリウム血症で、重症になると致死的な不整脈や心停止を引き起こすことがあります1)。

腎臓の機能が落ちていると高カリウム血症を起こす頻度が上がります。いまや「国民病」ともいわれる慢性腎臓病(CKD)は腎機能が低下する疾患で、高カリウム血症の原因になり得ます。CKDの患者数は成人の8人に1人とも言われていますが、認知度は高くありません2)。
CKDの治療では摂取するカリウム量をコントロールするため食事管理が必要となりますが、中には誤った認識のまま不適切な食事管理をしてしまっている人もいるといいます。そこで製薬会社のアストラゼネカ株式会社は、高カリウム血症と食事管理に関するセミナーを開催しました。セミナーには医師の菅野義彦先生(東京医科大学)と管理栄養士の宮澤靖先生(東京医科大学病院)が登壇し、食事管理のポイントなどを解説しました。
自分のカリウム値がわからない人は一度検査を

医師の菅野先生(東京医科大学)は「カリウムはすべての細胞の環境維持や、筋機能の調節を担っている」と説明しました。そして「高カリウム血症は病気ではなく、体の状態」としたうえで、「カリウムの血中濃度は普通に生活していれば正常値を維持できるけれども、病気にかかったりした場合は、数値を意識する必要がある」と解説しました。そもそも高カリウム血症は食事によりカリウムの摂取量が増えたり、排泄能力が落ちたり、腎機能が低下したりなど、「カリウムの摂取量と排泄量のバランスが悪くなったときに生じる」といいます。そのため、食事でカリウムの摂取量を調整する必要が生じるのです。
菅野先生は「カリウムの血中濃度の安全域は非常に狭いため、ほんのちょっとした変化が体の機能に影響を及ぼす」とし、「カリウム値は一般的な検診の検査項目には入っていないため、ご自身で一度は検査しましょう」と呼びかけました。
CKD患者さんは食事管理が必要
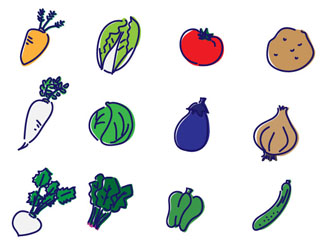
宮澤先生(東京医科大学病院)は、栄養士の観点から食事とカリウム管理について解説しました。成人1人1日当たりのカリウム目安摂取量は、男性は2,500mg、女性は2,000mgです3)。宮澤先生によると「一般的な健康の方であれば、通常の食事をしていればカリウムの過剰摂取はほぼない」といいます。ただしCKDなどで通院中の患者さんであれば、細かくカリウム量をコントロールするための食事管理が必要になります。
「患者さんの中には『野菜をたくさんとっているから健康』と言い切る方も多い」と宮澤先生。しかしカリウムは緑黄色野菜や果物、いも類に多く含まれるため、食べすぎには注意しなければなりません。食材からカリウム量を減らすポイントとして、「カリウムは水やお湯に溶けるので、野菜などは小さく切ってゆでこぼしたり流水にさらしたり、果物は缶詰のものを食べる」ことを挙げました。また「CKDはある程度、食事管理が必要な疾患です。定期的に受診をして、主治医や管理栄養士のチェックを受けるようにしましょう」と呼びかけました。
食事管理では日々の食事の材料や分量、回数を記録することが重要です。しかし、多忙や高齢などの理由で、正確に記録し続けるのが難しい場合もあるかもしれません。セミナーでは食事管理をサポートするアプリ「ハカリウム」が紹介されました。ハカリウムは料理を撮影するだけで簡単にカリウム量を測ることができるので、気になる方はインストールしてみてはいかがでしょうか。(QLife編集部)
1)American Heart Association: Life-Threatening Electrolyte Abnormalities. Circulation112 (24_supplement), p.IV-121-IV-125, 2005.[https://www.ahajournals.org/doi/epub/10.1161/CIRCULATIONAHA.105.166563](2023年1月6日閲覧)
2)日本腎臓病協会:慢性腎臓病(CKD)の普及・啓発.[https://j-ka.or.jp/ckd/](2022年12月28日閲覧)
3)「日本人の食事摂取基準」策定検討会:日本人の食事摂取基準(2020年版).
記事を読んでポイント獲得!

10pt 進呈!!
この記事を読んで
簡単なアンケートに回答すると、
"Amazonギフト券に交換できる"
QLifeポイントを獲得できます!
- この記事を読んだ人は
他にこんな記事も読んでいます。
掲載されている記事や写真などの無断転載を禁じます。