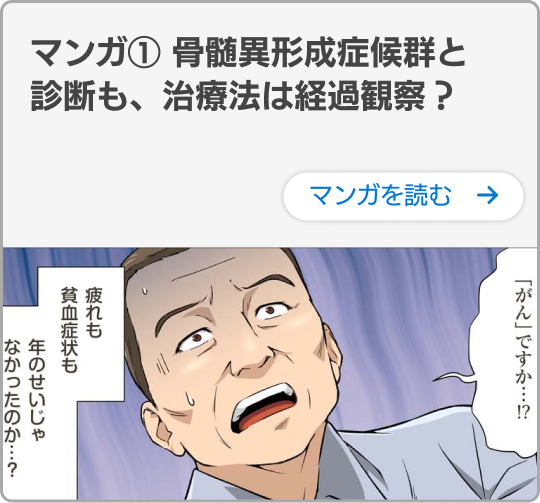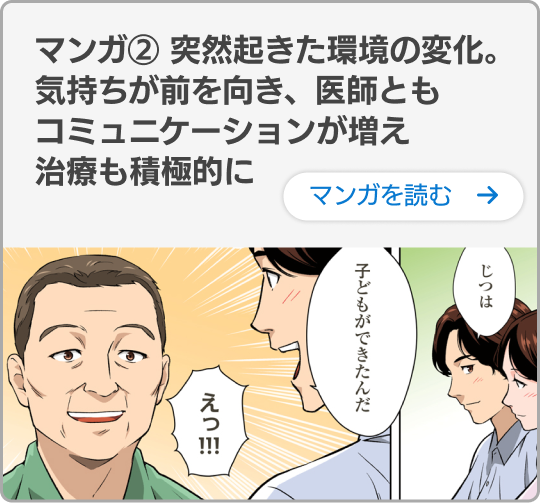症状のつらさ、改善したい気持ちを医師へ伝え続ける大切さ~貧血症状などがあっても経過観察が続いたことで、より良くなることを諦めてしまった”骨髄異形成症候群”の患者さんのケースから考える
[骨髄異形成症候群] 2024/10/25[金]
11月1日は、日本医師会が制定する、より良い医療の在り方を考える『いい医療の日』です。より良い医療のためには、医師だけでなく患者さん自身が意思を示し、自分の希望を伝えていくことが重要といわれています。一人ひとりが「いのちの主人公」であり、「からだの責任者」であることの自覚が大切です。しかし、病気と診断されたときや治療を継続していくなか、ご自身の思いや希望を医師にきちんと伝えられている方はどのくらいいらっしゃるのでしょうか。特に、治療や経過が長期におよぶ慢性疾患においては、医師へ「伝える」ということを諦めてしまわれる場合もあるのではないでしょうか。
今回は、慢性疾患の一つである骨髄異形成症候群(MDS)を例に、患者さんと医師のコミュニケーションの課題や在り方について、マンガと解説で考えていきたいと思います。MDSに限らず、進行が緩徐な慢性疾患全般に共通する課題と解決へのヒントを紹介していますので、ぜひご覧ください。
骨髄異形成症候群(MDS)とは?
MDSとは、赤血球や白血球、血小板などの血液細胞をつくる造血幹細胞に異常が起きる病気です。どの血液細胞の形や機能に異常が起こるのか、またその程度によって、めまいやだるさ、運動時の動悸や息切れ、感染しやすくなる、出血しやすくなるなどのさまざまな症状があらわれます。
治療はリスクにより異なります。例えば、低リスクで症状がある場合は血液細胞の減少を改善するための治療を行いますが、症状がない場合は経過観察となります。一方、高リスクの場合は急性白血病への移行を遅らせるための治療が行われます。リスクにかかわらず、貧血症状の改善や感染症への対策として支持療法※1が行われます。また、一部の方では治癒を目指す治療として、造血幹細胞移植が実施されます。
ちなみに10月25日は、MDSの認知度向上のための活動を行う『MDS awareness Day』です。この機会にMDSについても皆さんに理解を深めていただければと思います。
※1 支持療法:病気による症状や、治療による副作用を緩和するために行われる治療のこと。
●山口育子さん(認定NPO法人ささえあい医療人権センターCOML[コムル]理事長)からのメッセージ
より良い医療は、患者さんと医師が「協働」することで実現すると考えています。治療の主人公は患者さん自身です。治療方法を決めるのは自分自身という自覚を持ち、治療のために大切な情報である「自覚症状」を医師へ伝えることを諦めないでほしいと思います。また、「症状の変化」も重要な情報なのできちんと医師へ伝えていただきたいです。そして、医師の説明に納得できないときは「もう一度説明していただけますか」と何度でも質問することが大切です。患者さんと医師の「協働」には良い関係づくりが重要で、それは患者さんにも責任があります。より良い治療のためには、患者さん自身の努力の積み重ねがとても重要なのです。
●鈴木隆浩先生(北里大学 医学部 血液内科学 主任教授・血液内科長)からのメッセージ
MDSでは患者さんの年齢や合併症、MDSの状態などによって最適とされる治療方針が異なり、マンガに登場する前田さんのように経過観察をしばらく続けることもしばしばあります。治療期間が長い患者さんも多いため、その間には不安を感じることがあるかもしれません。そのときは、ご自身の不安や疑問を主治医に話してみてください。きっと何らかの対応があると思います。MDSの診療は患者さんと主治医の共同作業です。主治医から提案される医学的な対応と患者さんの受け止め方、主治医と患者さんのコミュニケーションが調和してはじめて効果を発揮します。本資材によって患者さんと医師の関係がより充実したものになり、患者さんの幸せに結びつくことを願っています。

北里大学 医学部 血液内科学 主任教授・血液内科長
1993年、東京大学医学部卒。2年間の研修の後、東京大学血液・腫瘍内科に入局し、2000年に博士号(医学)を取得。以後、東京大学、自治医科大学で血液学の研究、診療を行い、2016年より北里大学医学部血液内科主任教授。専門はMDSや再生不良性貧血などの骨髄不全症、赤血球系疾患。北里大学では血液疾患の研究、診療とともに、全国的に問題となっている血液疾患の地域診療連携について、大学・地域病院・在宅医のネットワークを構築し、患者と医療者がともに幸せになれる医療を模索している。

認定NPO法人ささえあい医療人権センターCOML[コムル]理事長
1989年、大阪教育大学卒。1992年秋に「ささえあい医療人権センターCOML(コムル)」のスタッフとなり、COMLの活動全般の運営に携わる。2002年から専務理事兼事務局長、2011年から理事長。ご自身のがん罹患経験をもとに、患者と医師が協働する医療の実現を目指した活動を行う、患者視点から医師とのコミュニケーションを考える専門家。著書に「賢い患者」(岩波書店、2018)がある。
提供:ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社
掲載されている記事や写真などの無断転載を禁じます。